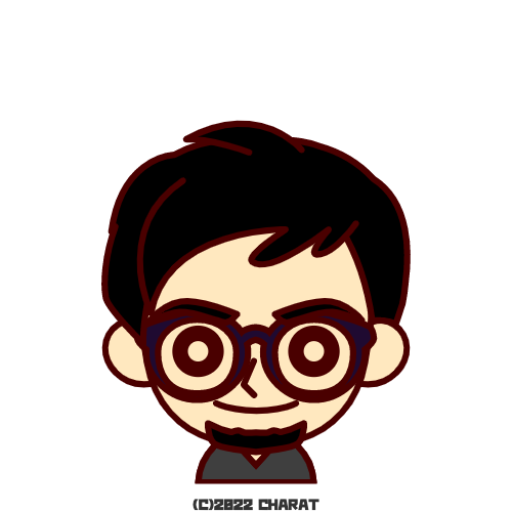「最近、軽自動車の排気量が770ccに拡大されるって本当?」
「もし変わるなら、いつからなの?」
そんな噂を耳にして、愛車の購入や買い替えのタイミングに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
日本の暮らしに欠かせない軽自動車ですが、その規格が変わるとなれば、税金や燃費、車の価格など、気になることがたくさんありますよね。
この記事では、「軽自動車の770cc化」という話題の真相に迫ります。
この記事でわかること
- 軽自動車770cc化の噂は本当?いつから始まるの?
- なぜ今、排気量アップが議論されているの?
- もし770ccになったら、税金や燃費、価格はどう変わる?
- 自動車メーカー各社の対応はどうなってる?
この記事を最後まで読めば、軽自動車の排気量に関するあなたの疑問がスッキリ解決し、安心して次のアクションを考えられるようになります。
今後の動向を見据え、賢いクルマ選びをするための知識を身につけましょう。
軽自動車の排気量770cc規格はいつから?噂と現実のギャップに迫る

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
結論からお伝えすると、2025年現在、軽自動車の排気量を770ccに拡大するという正式な発表や決定は、政府からも自動車メーカーからも一切ありません。
では、なぜこれほどまでに「770cc化」の噂が広まっているのでしょうか。それは、現在の軽自動車が抱える課題と、時代の変化が大きく関係しています。
現在、軽自動車の排気量は660cc以下に定められていますが、この規格が制定されたのは1990年。
当時と比べて、現代のクルマは衝突被害軽減ブレーキなどの安全装備や、快適な室内空間を実現するための装備が格段に増え、車両重量が重くなる傾向にあります。
そのため、現在の660ccエンジンでは、特に坂道や高速道路での走行時に「もう少しパワーが欲しい」と感じる場面が増えているのも事実です。
こうした背景から、ユーザーの満足度向上や、より効率的なエンジン開発を目指すために、規格そのものを見直すべきではないか、という議論が専門家や業界関係者の間で断続的に行われているのです。
しかし、規格変更は税金や保険制度にも大きな影響を与えるため、そう簡単には決定できません。
770cc化の話題は、あくまで将来の可能性を探る「議論の段階」であり、現時点では噂や憶測の域を出ない、というのが真実です。
現在の軽自動車規格と排気量制限の詳細を確認しよう
まずは、現在の軽自動車がどのような規格で定められているのか、基本をおさらいしておきましょう。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 排気量 | 660cc以下 |
| 全長 | 3.4m以下 |
| 全幅 | 1.48m以下 |
| 全高 | 2.0m以下 |
| 定員 | 4名以下 |
この日本独自のコンパクトな規格こそが、軽自動車の魅力の源泉です。
狭い道でも運転しやすく、税金や保険料が安いといった経済的なメリットは、この規格があるからこそ成り立っています。
しかし、技術の進歩により、より大きな排気量のエンジンでも優れた燃費性能や環境性能を実現できるようになってきました。
こうした技術的背景も、排気量規制の緩和が議論される一因となっています。
軽自動車770cc新規格が注目される経緯と社会的背景を徹底解説
では、なぜ「770cc」という具体的な数字が注目されるようになったのでしょうか。
その背景には、大きく3つの要因があります。
- 1.安全・快適装備の充実による車両重量の増加
近年の軽自動車は、普通車と遜色ないほど安全装備や快適装備が充実しています。
例えば、衝突被害軽減ブレーキ、複数のエアバッグ、電動スライドドア、大型ナビゲーションシステムなどです。
これらは安全で快適なドライブに貢献する一方で、車両重量を増加させる大きな要因となっています。
重くなった車体を660ccのエンジンで動かすには、より多くのパワーが必要となり、結果としてエンジンに負担がかかり、燃費の悪化や力不足感につながることがあります。
- 2.電動化(ハイブリッド・EV)への対応
環境問題への対応として、自動車業界全体でハイブリッド化やEV化が急速に進んでいます。
軽自動車も例外ではありませんが、現在の規格ではモーターやバッテリーを搭載するためのスペースや重量に厳しい制約があります。
排気量規格を拡大することで、エンジンとモーターを組み合わせた効率的なハイブリッドシステムの搭載や、より大容量のバッテリーを積んだEVの開発がしやすくなるというメーカー側の事情があります。
▼関連記事
【結論】軽自動車にプラグインハイブリッドは存在しない?理由と代替車を解説
-

【結論】軽自動車にプラグインハイブリッドは存在しない?理由と代替車を解説
「軽自動車にもプラグインハイブリッドカー(PHEV)ってあるのかな?」 「燃費が良くて環境にも優しい ...
続きを見る
- 3.走行性能向上に対するユーザーの期待
「軽自動車はパワーがない」というのは、もはや過去の話になりつつありますが、それでも普通車と比較すると、高速道路での合流や追い越し、急な坂道などでは力不足を感じる場面も少なくありません。
ユーザーからは、日常生活での使いやすさはそのままに、長距離移動でもストレスのない、より余裕のある走行性能を求める声が高まっています。
▼関連記事
軽自動車で高速道路はきつい?原因と対策、おすすめ車種を紹介!
-

軽自動車で高速道路はきつい?原因と対策、おすすめ車種を紹介!
「軽自動車で高速道路を走るのは、やっぱりきつい?」 「合流や追い越しで、パワー不足を感じそうで不安… ...
続きを見る
これらの要因が複雑に絡み合い、「排気量を770cc程度まで引き上げることで、これらの課題を解決できるのではないか」という議論につながっているのです。
軽自動車の排気量770cc化の真相は?過去の規格改定の歴史から探る
軽自動車の規格が変更されるのは、今回が初めてではありません。過去にも、時代の要請に応じて何度か規格改定が行われてきました。
例えば、1976年に排気量が360ccから550ccへ引き上げられた背景には、厳しくなった排ガス規制への対応や、高速道路網の整備に伴う動力性能向上の必要性がありました。
また、現行の660cc規格が導入された1990年には、さらなる安全性向上が求められていました。
このように、軽自動車の規格は、その時々の社会的な要請や技術の進歩に合わせて変化してきた歴史があります。
現在の「770cc化」の議論も、安全性の向上や電動化といった現代的な課題に対応するための、ごく自然な流れの中にあると捉えることができます。
しかし、過去の改定と同様に、実現には多くの課題をクリアする必要があるため、慎重な議論が続いているのが現状です。
軽自動車の排気量規格の変遷:昭和から平成、そして令和へ

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
日本のモータリゼーションと共に歩んできた軽自動車。その歴史は、排気量規格の変遷の歴史でもあります。
ここで、昭和から令和に至るまでの規格の移り変わりを振り返ってみましょう。
軽自動車の規格改定による排気量の推移を具体的に紹介
軽自動車の排気量は、誕生から現在までに大きく4回、重要な変更を遂げてきました。
| 年代 | 排気量上限 | 主な社会的背景・目的 |
|---|---|---|
| 1949年 | 150cc | 軽自動車制度の誕生 |
| 1955年 | 360cc | 国民車構想、モータリゼーションの幕開け |
| 1976年 | 550cc | 排ガス規制強化、安全性・動力性能の向上 |
| 1990年 | 660cc | 高速道路での安全性向上、物品税の改正 |
このように、軽自動車の規格は、日本の経済成長や社会インフラの整備、環境問題への意識の高まりといった、時代の変化を色濃く反映しながら見直されてきました。
それぞれの改定を経て、軽自動車はより安全で、快適で、実用的な乗り物へと進化を遂げてきたのです。
平成時代の軽自動車人気モデルと排気量の設定を振り返る
現行の660cc規格が始まった平成時代は、軽自動車が飛躍的な進化を遂げ、その人気を不動のものにした時代と言えるでしょう。
1993年にスズキから発売された「ワゴンR」は、「ハイトワゴン」という新しいジャンルを確立し、それまでの「軽は狭くて実用性が低い」というイメージを覆しました。
これにダイハツ「ムーヴ」やホンダ「ライフ」などが続き、軽自動車市場は一気に活性化しました。
これらのモデルは、広い室内空間と使い勝手の良さで、セカンドカーとしてだけでなく、ファーストカーとしても十分に通用する実力を備えていました。
また、平成後半になると、ターボエンジンやCVT(無段変速機)の技術が成熟し、660ccという限られた排気量の中でも、力強い走りと優れた燃費性能を両立できるようになりました。
さらに、衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全装備も積極的に採用され始め、軽自動車は「安かろう悪かろう」から「小さくても高性能」なクルマへと大きく価値観を変えたのです。
▼関連記事
-

軽自動車とコンパクトカー、寿命と耐久性の本当の違い
「軽自動車って、やっぱりコンパクトカーより寿命が短いのかな?」 「初めて車を買うけど、長く乗れるのは ...
続きを見る
現在の軽自動車と770cc構想の違いを一覧で比較!乗用車との境界は変わるのか

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
もし、本当に軽自動車の排気量が770ccになったら、私たちのカーライフはどう変わるのでしょうか。
現在の660cc規格と、構想段階の770cc規格を比較し、その変化を予測してみましょう。
| 項目 | 現行の軽自動車 (660cc) | 770cc構想の軽自動車 (仮) | 変化の予測 |
|---|---|---|---|
| 走行性能 |
|
| 大幅に向上 |
| 燃費 |
|
| 使い方によっては向上 |
| 軽自動車税 |
|
| 大幅に増加 |
| 車両価格 |
|
| 上昇 |
| メリット |
|
| 快適性・安全性が向上 |
| デメリット |
|
| 経済的負担が増加 |
このように、770cc化は走行性能の向上という大きなメリットをもたらす一方で、税金や車両価格の上昇というデメリットも伴います。
これまでの「安くて手軽」という軽自動車の魅力が薄れ、コンパクトカーとの境界線が曖昧になる可能性があります。
▼関連記事
-

維持費が変わらないって本当?軽自動車とコンパクトカーの実態
「軽自動車は維持費が安いって聞くけど、最近のコンパクトカーとあまり変わらないって本当?」 「結局、自 ...
続きを見る
軽自動車のガソリン使用量や燃費性能は770ccでどう変わるのか
「排気量が大きくなると、燃費が悪くなるのでは?」
と心配する方も多いでしょう。確かに、同じようにエンジンを回せば、排気量が大きい方がガソリンを多く消費します。
しかし、一概に燃費が悪化するとは限りません。むしろ、実用燃費は向上する可能性も秘めています。
現在の660ccの軽自動車で高速道路を走る場合、エンジンを高い回転数で維持し続けなければならず、かえって燃費が悪化することがあります。
一方、排気量に余裕のある770ccエンジンなら、より低い回転数でスムーズに巡航できるため、結果的にガソリンの消費を抑えられる可能性があるのです。
エンジンに余裕が生まれることで、アクセルを深く踏み込む機会が減り、市街地でのストップ&ゴーにおいても、燃費に有利に働く場面が期待できます。
もちろん、最新のハイブリッド技術などと組み合わせることが前提となりますが、「排気量アップ=燃費悪化」という単純な式は成り立たないかもしれません。
排気量アップによる走行性能・燃費改善の可能性とメリット
排気量アップがもたらす最大のメリットは、やはり走行性能の劇的な向上です。
- 高速道路での安定性: 合流や追い越しがスムーズになり、長距離運転の疲労が軽減される。
- 坂道での力強さ: 多人数乗車時やエアコン使用時でも、ストレスなく坂道を登れる。
- 静粛性の向上: エンジンを無理に回す必要がなくなるため、車内が静かになり、会話や音楽をより楽しめる。
- 振動の低減: エンジンの回転が滑らかになることで、不快な振動が減り、乗り心地が向上する。
これらのメリットは、日常のちょっとした運転から休日のロングドライブまで、あらゆるシーンで「運転の質」を高めてくれます。
安全性や快適性といった、現代のクルマに求められる基本的な性能を底上げする上で、排気量の拡大は非常に有効な手段と言えるでしょう。
軽自動車770cc化による新車価格や税制優遇への影響を詳しく解説
一方で、ユーザーにとって最も気になるのが経済的な負担です。
- 税金
現在、軽自動車税(種別割)は年間10,800円(標準税率)です。
もし770cc化によって軽自動車の枠組みが変更された場合、排気量1,000cc以下の普通乗用車と同じ年間25,000円(2019年10月1日以降の新車登録車)に引き上げられる可能性があります。
これは、年間約14,000円の負担増となり、維持費の安さという軽自動車の大きなメリットが損なわれることになります。
- 車両価格
新しいエンジンや、それに対応する車体を開発するには、莫大なコストがかかります。そのコストは当然、車両価格に反映されます。
現在の軽自動車の人気モデルは150万円~200万円が中心ですが、770cc化が実現すれば、数十万円単位での価格上昇は避けられないでしょう。
このように、規格変更はユーザーの経済的負担に直結するため、政府もメーカーも非常に慎重な姿勢を取らざるを得ないのです。
▼関連記事
-

軽自動車に200万円は後悔する?失敗談と選び方のコツ
「最近の軽自動車って、オプションをつけたら200万円を超えることも珍しくないらしい・・・。」 「乗り ...
続きを見る
自動車メーカーが排気量変更に対応するために必要な対応策
自動車メーカーにとっても、規格変更は大きな挑戦です。
- 新エンジンの開発: 770ccという新しい排気量で、パワー、燃費、環境性能を高い次元でバランスさせたエンジンをゼロから開発する必要がある。
- 車体の再設計: パワーアップしたエンジンに合わせて、ボディ剛性の強化やサスペンション、ブレーキの見直しなど、車体全体の設計変更が求められる。
- 生産ラインの改修: 新しいエンジンや車体を生産するために、工場の設備を大幅に改修する必要があり、巨額の投資が必要となる。
- 部品供給網の再構築: エンジン部品をはじめ、関連する多くの部品を新規に調達する必要があり、サプライヤーとの調整も不可欠。
これらの対応には、長い年月と膨大なコストがかかります。
そのため、メーカーとしては、規格変更の正式な決定がない限り、本格的に動き出すことは難しいのが実情です。
各自動車会社の軽自動車770cc新規格への対応方針と最新動向を探る

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
では、軽自動車市場を牽引する各メーカーは、この「770cc化」の動きをどう捉えているのでしょうか。
現時点ではどのメーカーも公式なコメントは出していませんが、その姿勢や今後の戦略を推測することは可能です。
軽自動車メーカー各社の新車開発・販売戦略の変化と今後の展望
もし規格変更が現実のものとなれば、各メーカーはそれぞれの強みを活かしたクルマ作りを進めるでしょう。
- スズキ
軽量化技術と効率的なエンジン開発に定評があり、770cc化されてもクラス最高水準の燃費性能を追求してくることが予想されます。
- ダイハツ
「DNGA(Daihatsu New Global Architecture)」という設計思想のもと、低コストで高品質なクルマ作りに強みを持っています。
価格上昇を抑えつつ、走行性能と安全性を両立させたモデルを投入する可能性があります。
- ホンダ
N-BOXで培った「M・M思想(マン・マキシマム/メカ・ミニマム)」をさらに進化させ、770ccのパワーを活かした、より広く快適な室内空間を持つモデルを開発するかもしれません。
- 三菱・日産
電動化技術で先行しており、770ccエンジンとモーターを組み合わせた独自のe-POWERのようなシステムや、より高性能な軽EVの開発に力を入れる可能性があります。
いずれにせよ、規格変更はメーカー間の競争をさらに激化させ、より個性的で魅力的な軽自動車が生まれるきっかけになるかもしれません。
ホンダ・スズキ・ダイハツ各社の排気量引き上げに対する姿勢
軽自動車市場のトップを走るホンダ、スズキ、ダイハツの3社ですが、現時点では排気量引き上げに対して公式なスタンスを表明していません。
インターネット上では「2025年モデルから770ccになる」といった動画やSNSの投稿が見られますが、これらはメーカーや国土交通省から発表された事実に基づくものではなく、あくまで個人の憶測です。
もちろん、各社とも将来の可能性に備えて水面下での研究開発は進めていると考えられますが、税制やインフラなど、社会全体に大きな影響を与える問題であるため、業界団体などを通じて慎重に議論の推移を見守っている段階と言えるでしょう。
トヨタ・日産・スバルは軽自動車規格変更にどう対応するのか?
トヨタ、日産、スバルも軽自動車を販売していますが、その多くはダイハツやスズキ、三菱からのOEM(相手先ブランドによる生産)供給によるものです。
そのため、これらのメーカーが独自に排気量変更を主導することは考えにくく、基本的には供給元であるメーカーの方針に追随する形となります。
ただし、トヨタの「Toyota Safety Sense」のように、自社が開発した先進安全技術をOEM供給される軽自動車にも展開するケースはあります。
もし規格変更が行われるとすれば、各社が持つ独自の安全思想や環境技術を、新しい規格の軽自動車にどのように反映させていくのかが注目されます。
軽自動車と普通乗用車の規約・ポリシーの違いをわかりやすく整理
770cc化の議論で重要なのは、これが「軽自動車」と「普通乗用車(特にコンパクトカー)」の境界線を曖昧にする可能性があるという点です。
| 軽自動車 (現行) | コンパクトカー (例: ヤリス、フィット) | |
|---|---|---|
| 税金 | 安い (軽自動車税) | 高い (自動車税) |
| 高速料金 | 安い (軽自動車料金) | 普通車料金 |
| 車庫証明 | 不要な地域が多い | 原則必要 |
| 車両価格 | 比較的安い | 軽自動車より高い傾向 |
| 走行性能 | 街乗り中心 | 長距離も快適 |
もし軽自動車が770ccになり、税金や車両価格がコンパクトカーに近づくのであれば、ユーザーは「どちらを選ぶべきか」という新たな選択を迫られることになります。
走行性能や室内の広さで勝るコンパクトカーを選ぶ人が増え、軽自動車市場そのものが縮小してしまうリスクも指摘されています。
軽自動車が770ccに規格拡大した場合のメリット・デメリット一覧

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
これまでの情報を整理し、770cc化が実現した場合のメリットとデメリットを一覧で見てみましょう。
【メリット】
- 走行性能の大幅な向上: 高速道路や坂道での運転が格段に楽になり、長距離移動の疲労が軽減される。
- 静粛性・快適性の向上: エンジン音が静かになり、乗り心地が良くなることで、ドライブの質が向上する。
- 安全性の向上: パワーに余裕が生まれることで、より高度な安全装備の搭載や、車体剛性の強化がしやすくなる。
- デザインの自由度アップ: エンジンサイズの制約が緩和され、より多様で魅力的なデザインのクルマが生まれる可能性がある。
【デメリット】
- 維持費の増加: 軽自動車税や任意保険料が上昇し、経済的なメリットが薄れる。
- 車両価格の高騰: 新しいエンジンの開発費などが価格に転嫁され、購入のハードルが上がる。
- 燃費悪化のリスク: 運転スタイルによっては、燃費が悪化する可能性がある。
- 「手軽さ」の喪失: 車両サイズは変わらなくても、価格や維持費の面で「気軽に乗れる」存在ではなくなるかもしれない。
排気量拡大がもたらす最高速度・安全性能の比較と個人ユーザーの声
最高速度については、現在の軽自動車も普通車も、高速道路での法定速度は同じ100km/h(一部区間120km/h)であり、メーターも140km/hまでしか刻まれていません。
排気量が拡大されても、この最高速度自体が変わることはないでしょう。
変わるのは、そこに至るまでの加速性能や、速度を維持する際の余裕です。
安全性能については、間違いなく向上が期待できます。重くなった車体を確実に制御するためのブレーキ性能の強化や、より高度な運転支援システムの搭載が可能になります。
この規格変更について、ユーザーからは様々な声が上がっています。
【賛成派の声】
「高速をよく使うから、パワーが上がるなら大歓迎!」
「今の軽は少しうるさい。静かになるなら高くてもいい。」
「安全性が高まるなら、その方が安心できる。」
【反対派の声】
「税金が上がるなら、今のままで十分。」
「軽の良さは安さなのに、意味がなくなる。」
「これ以上高くなったら、もう買えない。」
このように、ユーザーが軽自動車に何を求めるかによって、賛否両論あるのが現状です。
軽自動車の排気量規格拡大はいつ公開?今後のスケジュール予想

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
では、結局のところ、軽自動車の排気量規格拡大は「いつ」行われる可能性があるのでしょうか。
前述の通り、現時点で具体的なスケジュールは存在しません。
過去の規格改定が約15年~20年のサイクルで行われてきたことを考えると、現行の660cc規格が導入された1990年から30年以上が経過しており、いつ大きな見直しがあってもおかしくない時期に来ているのは確かです。
しかし、現在は自動車業界全体が「100年に一度の大変革期」にあり、ガソリン車からEVへのシフトという大きな課題に直面しています。
そのため、単純な排気量アップではなく、将来の電動化を見据えた新しい規格(例えば、モーター出力やバッテリー容量を基準とした「軽EV」の規格など)が検討される可能性も十分に考えられます。
いずれにせよ、規格変更には法改正や社会的なコンセンサス形成が必要であり、実現するとしても数年単位の時間がかかると予想されます。
今後数年以内に突然規格が変わる、ということは考えにくいでしょう。
軽自動車の排気量770cc新規格に関する業界・行政の意見やコメント集
この問題について、業界団体や行政はどのような見解を示しているのでしょうか。
- 日本自動車工業会(自工会)
会長会見などでは、軽自動車が日本の国民の足として重要な役割を担っていることを強調しつつ、電動化や安全性向上といった課題に対応していく必要性について言及しています。
ただし、具体的な排気量アップについては、慎重な姿勢を崩していません。
- 国土交通省
自動車の安全・環境基準を所管する立場として、常に最新の技術動向や社会情勢を注視しています。
規格変更については、ユーザーへの影響や国際的な整合性など、多角的な視点から検討する必要があるとしており、特定の結論ありきで議論を進めているわけではないようです。
総じて、関係各所は軽自動車の将来について問題意識を共有しつつも、その影響の大きさから、非常に慎重に議論を進めている段階と言えます。
まとめ:軽自動車の770cc化は現状検討段階、今後の動向も要チェック

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
最後に、この記事の要点をまとめます。
【今回のまとめ】
- 軽自動車の770cc化は、2025年現在、正式な決定はなく「噂・検討」の段階。
- 背景には、安全・快適装備の充実による車両重量の増加と、それに伴うパワー不足感がある。
- もし実現すれば、走行性能は向上するが、税金や車両価格も上昇する可能性が高い。
- 今後の電動化への流れが、規格変更の議論に大きく影響する可能性がある。
- 正式な情報は、政府や自動車メーカーの公式サイトで確認することが重要。
軽自動車の排気量規格の話題は、私たちのカーライフに直結する重要なテーマです。
今後も最新情報に注目していく必要があります。
あなたに合った一台を見つけよう!賢いクルマ選びの選択肢
「規格が変わるのを待っていられない」
「今すぐクルマが必要」
という方も多いでしょう。 幸い、現在の660cc軽自動車は非常に完成度が高く、魅力的なモデルがたくさんあります。また、中古車やカーリースなど、購入方法も多様化しています。
あなたのライフスタイルや予算に合わせて、最適な一台を見つけるための選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
▼最新の軽自動車の性能を、まずは試乗で体感したい方へ
最新モデルの進化には驚くべきものがあります。まずは公式サイトで情報をチェックし、お近くのディーラーで試乗してみるのがおすすめです。
▼価格を抑えつつ、豊富な選択肢から安心して選びたい方へ
「新車は高いけど、程度の良いクルマが欲しい」という方には、中古車がぴったり。大手なら保証も充実しているので安心です。
豊富な在庫から、あなたの希望に合った一台がきっと見つかります。
▼ガリバーの中古車在庫をチェックしてみる(中古車・PR)
▼関連記事
ガリバーはやばい?やめとけと言われる理由と中古車購入で失敗しない対策
-

ガリバーはやばい?やめとけと言われる理由と中古車購入で失敗しない対策
「あ、このN-BOXいいな!でも販売店がガリバーか…」 中古車サイトを見ていて、そんな ...
続きを見る
ガリバーで車を買うなと言われる5つの理由|それでも後悔しない人の共通点
-

ガリバーで車を買うなと言われる5つの理由|それでも後悔しない人の共通点
「そろそろ車が欲しいな」と思ってネットで調べていると、検索候補に「ガリバーで車を買うな」という不穏な ...
続きを見る
中古車を買うときの判断材料はこちらの記事「後悔しない中古軽自動車の選び方と人気おすすめ車種を徹底解説」で詳しくまとめています。
-

後悔しない中古軽自動車の選び方と人気おすすめ車種を徹底解説
「中古で軽自動車を買いたいけど、どんな点に注意すればいいんだろう…」 「買ってから後悔するような失敗 ...
続きを見る
▼初期費用ゼロ!月々定額で気軽に新車に乗りたい方へ
「頭金を用意するのが大変」「税金やメンテナンスの支払いを気にせず乗りたい」という方には、カーリースがおすすめです。
月々の料金に全てコミコミで、手軽に新車ライフを始められます。
▼月々定額で新車に乗り換える(カーリース・PR)
月々定額のカーリース【SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)】
▼関連記事
軽自動車リースのおすすめ比較【2026年最新版】人気会社・車種・料金を徹底解説
-

軽自動車リースのおすすめ比較【2026年最新版】人気会社・車種・料金を徹底解説
「そろそろ軽自動車が欲しいけれど、新車は高くて手が出ない…」 「初期費用を抑えて、無理なく車に乗りた ...
続きを見る
-

SOMPOで乗ーるのデメリット7選と対策【契約前必読】
「あこがれの軽自動車や輸入車に新車で乗りたいけれど、頭金や維持費が心配…」 「カーリースなら月々定額 ...
続きを見る