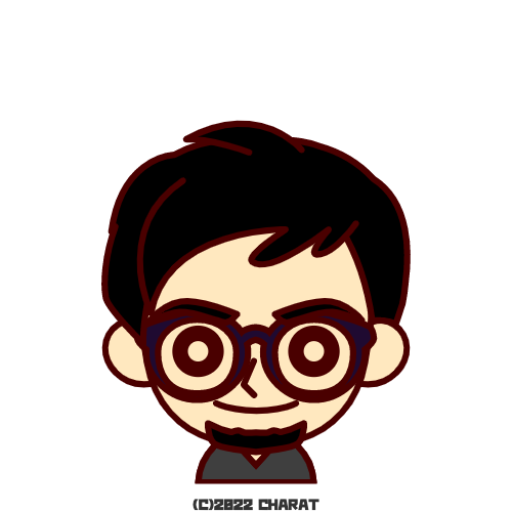「軽自動車は好きだけど、もう少しパワーがあれば…」
「高速道路や坂道で、ちょっと物足りなさを感じる」
そんな風に思ったことはありませんか?軽自動車のパワーに、もどかしさを感じている方は少なくありません。
そして、そのパワーの「上限」とされているのが「64馬力」という数値です。
「64馬力以上にパワーアップしたら、車検は通らないんだろうか?」
「そもそも、なぜ64馬力なんていう中途半端な規制があるの?」
そんな疑問をお持ちのあなたのために、この記事では軽自動車の馬力と車検にまつわる情報を徹底的に解説します。
この記事でわかること
- 軽自動車の馬力はなぜ64馬力に規制されているのか
- 64馬力以上に改造しても車検を通すための具体的な方法
- パワーアップ改造における注意点と合法的なチューニング
- チューニングにおすすめの人気軽スポーツカーモデル
- 馬力アップに伴う保険や税金への影響
この記事を読めば、軽自動車の馬力規制に関する長年の疑問がスッキリ解決し、安全に理想のカーライフを楽しむための一歩を踏み出せるはずです。
なぜ軽自動車の馬力は64馬力まで?意外と知らない規制の詳細を解説!

スズキ・アルトワークス公式より
軽自動車のカタログを見ると、ターボ車の最高出力はどれも判で押したように「64馬力」と記載されています。
実はこれ、法律で定められた義務ではなく、自動車メーカー間の「自主規制」によるものなのです。
この自主規制が生まれた背景には、1980年代の自動車業界における熾烈なパワー競争と、それに伴う安全性への懸念がありました。
1987年、スズキが発売した初代「アルトワークス」は、わずか550ccのターボエンジンで64馬力という、当時としては驚異的なパワーを叩き出しました。
これが引き金となり、ダイハツや三菱なども追随し、軽自動車の馬力は一気に高まっていったのです。
しかし、当時の軽自動車は現在の車に比べて、
- 車体の剛性が低く、ボディがもろかった
- 車重が非常に軽く、スピードを出すと不安定になりやすかった
といった弱点がありました。パワーだけが先行し、車体の安全性が追いついていない状況は、交通事故の増加を招く危険性をはらんでいました。
この状況を憂慮した当時の運輸省(現在の国土交通省)からの要請を受け、1989年、自動車工業会が「64馬力」を上限とする自主規制を設けることで合意。
以来、30年以上経った現在でも、この自主規制は日本の自動車メーカーによって守られ続けているのです。
64馬力規制が誕生した理由と日本の軽自動車の歴史を辿ろう
日本の軽自動車史を振り返ると、1980年代はまさに「パワーウォーズ」の時代でした。
好景気を背景に自動車が急速に普及し、人々は車に「速さ」や「高性能」を求めるようになります。
この流れは普通車だけでなく、軽自動車にも波及しました。各メーカーはターボチャージャーを搭載し、競い合うように馬力を向上させていきました。
スズキ「アルトワークス」の登場は、その競争の頂点とも言える出来事でした。しかし、前述の通り、過度なパワー競争は安全性の問題を浮き彫りにします。
スピードの出しすぎによる重大事故の増加が社会問題となり、行政が介入せざるを得ない状況になったのです。
実は当時、同様の自主規制は他のカテゴリーにも存在しました。
- 普通車:280馬力
- 二輪車:100馬力(国内仕様)
これらもすべて、過度な性能競争による事故増加を防ぐための措置でした。中でも軽自動車は、税制面で優遇される日本独自の規格であり、ボディサイズや排気量に厳しい制限があります。
その小さな枠の中で過剰なパワーを追求することは、安全性の観点から特に問題視されたのです。
時代は移り、車の安全技術は飛躍的に向上しましたが、軽自動車の64馬力自主規制は今なお続いています。
これは、軽自動車が持つ「経済性」「手軽さ」といった本来のメリットと、安全性のバランスを保つための知恵とも言えるでしょう。
馬力規制が無くなったら軽自動車市場はどう変わる?
「もし、64馬力の自主規制がなくなったら?」と想像したことがある方もいるでしょう。馬力規制が撤廃された場合、様々な変化が予測されています。
まず間違いなく起こるのは、メーカー間の新たなパワー競争です。
各社は技術の粋を集め、70馬力、80馬力、あるいは100馬力を超えるような軽自動車を開発するでしょう。
市場にはパワフルな軽スポーツモデルが溢れ、車好きにとっては夢のような時代が到来するかもしれません。
しかし、その一方で多くの課題も浮上します。
- 燃費の悪化
高出力なエンジンは、一般的に燃費が悪くなる傾向にあります。
軽自動車の大きな魅力である「経済性」が損なわれる可能性があります。
- 維持費の増加
パワーアップに伴い、エンジンオイルなどの消耗品にかかる費用や、税金・保険料が上昇する可能性があります。
- 車両価格の高騰
高性能なエンジンや、パワーに耐えうる強靭な車体を開発するにはコストがかかります。
その結果、車両価格全体が上昇することも考えられます。
- 安全性の再検討
スピードが出やすくなる分、事故のリスクは高まります。
より高度な安全装備が必須となり、それがさらなる価格上昇につながるという側面もあります。
馬力規制の撤廃は、軽自動車の走りを劇的に変える可能性を秘めていますが、同時に「安くて手軽な市民の足」という軽自動車の根幹を揺るがしかねない、諸刃の剣になるでしょう。
軽自動車の馬力アップは本当に車検が通らない?基礎知識をチェック!

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
さて、ここからが本題です。
「64馬力を超えるように改造した軽自動車は、車検に通らないのか?」という最大の疑問にお答えします。
結論から言うと、改造内容によっては、軽自動車のままでは車検に通らなくなるが、普通車登録し直せば車検を通すことは不可能ではありません。
重要なのは、軽自動車が「軽自動車」として認められるための規格を理解することです。
| 項目 | 軽自動車の規格 |
|---|---|
| 全長 | 3.4m以下 |
| 全幅 | 1.48m以下 |
| 全高 | 2.0m以下 |
| 排気量 | 660cc以下 |
馬力を上げるチューニングを行ったとしても、上記の規格をすべて満たしていれば、基本的には「軽自動車」として扱われます。
しかし、大幅な馬力アップを目指す改造の中には、この規格を超えてしまうものがあります。
そうなった場合、黄色いナンバーの軽自動車として乗り続けることはできず、「小型乗用車(5ナンバー)」や「普通乗用車(3ナンバー)」として登録し直す「構造変更検査」という手続きが必要になります。
もし軽自動車が馬力アップしたら?64馬力以上の車検対応のポイントとは
64馬力を超えるように改造した軽自動車で車検をクリアするためには、いくつかの重要なポイントがあります。
まず大前提として、道路運送車両法で定められた「保安基準」をすべて満たしている必要があります。
これは、馬力に関係なくすべての車に課せられるルールです。
その上で、馬力アップ改造で特に注意すべきポイントは以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 排気ガスと騒音の規制値をクリアする |
|
| 軽自動車の規格(寸法・排気量)を超えない |
|
| 違法な改造を行わない |
|
これらのポイントを押さえ、信頼できる知識と技術を持ったプロのショップに相談しながら改造を進めることが、合法的にパワーアップを楽しむための鍵となります。
車検に落ちないための馬力チューニングの注意点
「ちょっとパワーを上げるだけ」のつもりが、気づけば車検に通らない「違法改造になっていた…」というケースは後を絶ちません。
ここでは、特に陥りやすいチューニングの注意点を解説します。
- ECU(エンジン・コントロール・ユニット)の書き換え
エンジンの燃料噴射量や点火タイミングを制御しているコンピューター(ECU)のデータを書き換えることで、手軽に馬力を上げることができます。
しかし、知識のないまま安易に行うと、排気ガス規制値をオーバーしたり、エンジンに深刻なダメージを与えたりするリスクがあります。
信頼できる実績のあるチューニングショップに依頼しましょう。
- タービンの交換
ターボ車の場合、より大きなタービンに交換することで大幅な馬力アップが可能です。しかし、パワーが上がる分、エンジンや駆動系への負担も増大します。
冷却系(ラジエーターやオイルクーラー)の強化や、クラッチの強化など、他の部分とのバランスを考えたトータルチューニングが不可欠です。
- 吸排気系のカスタム
エアクリーナーをキノコ型と呼ばれるタイプに交換したり、抜けの良いマフラーに交換したりするのは定番のチューニングです。
しかし、吸気音が大きすぎたり、マフラーの音量が規制値を超えたりすると車検に通りません。
また、近年の車はマフラーの取り付け位置や向きも厳しくチェックされるため、注意が必要です。
自分でパーツを取り付けるDIYチューニングも車の楽しみ方の一つですが、車検や安全性に関わる部分は、プロの目で確認してもらうことを強くおすすめします。
車検で問題になる軽自動車パワーアップ改造の具体例と対策方法
実際に、どのような改造が車検で問題になるのでしょうか。
具体的な例とその対策を見ていきましょう。
| 改造の具体例 | なぜ問題になるか | 対策方法 |
|---|---|---|
| 排気量アップ(ボアアップ) |
|
構造変更検査を受け、普通車として登録する。 |
| タービン交換による大幅な馬力アップ |
|
ブレーキや足回りを強化し、安全性を確保した上で、専門ショップに相談する。
場合によっては構造変更を検討。 |
| オーバーフェンダーの装着 |
|
構造変更検査を受け、普通車として登録する。
その際、タイヤやホイールがフェンダーからはみ出さないように注意。 |
| 触媒(キャタライザー)の取り外し |
|
絶対に行わない。スポーツ触媒など、浄化性能を持つ車検対応品に交換する。 |
| 極端なローダウン |
|
車高調整式サスペンション(車高調)を導入し、車検時には規定の高さに調整する。 |
これらの改造を行う場合は、「軽自動車のままで乗りたい」のか、「普通車になっても良いからパワーを追求したい」のか、自分の目的を明確にすることが重要です。
その上で、法規を守りつつ理想の車に近づける方法を、チューニングに精通した専門家と一緒に探していくのが最善の道と言えるでしょう。
人気の軽スポーツカーモデルおすすめTOP5

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
ここでは、チューニングベースとしても人気が高く、ノーマルのままでも走りが楽しい軽スポーツカーをランキング形式で5台ご紹介します。
第1位:ホンダ S660

ホンダ・S660公式
軽自動車の枠を超えた本格ミッドシップ・オープンスポーツ。エンジンを車体中央に配置するMRレイアウトにより、コーナリング性能は抜群です。
生産は終了しましたが、中古車市場では今なお絶大な人気を誇ります。
- 中古車でしか手に入らない希少性
- 意のままに操れるハンドリング
- アフターパーツが豊富でカスタムの幅が広い
▼関連記事
-

-
軽自動車でサーキットデビュー!おすすめスポーツカー徹底比較
「サーキットを走ってみたいけど、スポーツカーは高くて手が出せない…」 「軽自動車でサーキット走行なん ...
続きを見る
第2位:スズキ アルトワークス

スズキ・アルトワークス公式より
軽ホットハッチの代名詞。軽量なボディにパワフルなターボエンジンを搭載し、キビキビとした加速が魅力です。
実用性も兼ね備えており、普段使いからサーキット走行までこなせるオールラウンダーです。
- 圧倒的な軽さとパワーウェイトレシオ
- 比較的リーズナブルな価格帯
- チューニング次第で驚くほどの速さを発揮
▼関連記事
-

-
軽自動車の加速性能はパワーウェイトレシオで決まる!
軽自動車の購入を検討しているあなたにとって、「加速性能」は気になるポイントの一つではありませんか? ...
続きを見る
-

-
アルトワークスの0-100km/h加速と歴代最速モデル比較
「軽自動車なんて遅いし、合流や坂道でストレスが溜まるんじゃないの?」 「アルトワークスって速いと聞く ...
続きを見る
第3位:ダイハツ コペン

ダイハツ・コペン Cero公式
おしゃれなデザインと電動開閉式ルーフが魅力の軽オープンカー。気分に合わせてボディ外板を着せ替えできる「DRESS-FORMATION」もユニークです。
見た目だけでなく、走りも本格的で、チューニングベースとしても人気があります。
- 気軽にオープンエアモータリングが楽しめる
- 初代から現行までモデルが豊富
- カスタムパーツが多く、個性を出しやすい
▼関連記事
-

-
コペン セロで後悔した瞬間と満足できる選び方
「街で見かける丸目の可愛いオープンカー、ダイハツ コペン セロ。見た目に一目惚れして購入を考えている ...
続きを見る
【2026年生産終了】コペン ローブは後悔する?新車・中古車の賢い選び方
-

-
【2026年生産終了】コペン ローブは後悔する?新車・中古車の賢い選び方
ダイハツの軽オープンスポーツカー「コペン ローブ」。 流麗でスタイリッシュなデザインは ...
続きを見る
第4位:スズキ ジムニー

スズキ・ジムニー公式
本格的な悪路走破性を持つ、世界でも類を見ない軽オフローダー。その無骨なスタイルとカスタムのしやすさから、オフロードファン以外からも絶大な支持を得ています。
リフトアップやタイヤ交換で、唯一無二の一台を作り上げる楽しみがあります。
- 他の軽にはない圧倒的な存在感
- 悪路走破性は折り紙付き
- カスタムパーツの市場が非常に大きい
▼関連記事
ジムニーのミディアムグレーは後悔する?失敗ポイントと対策・口コミを徹底まとめ
-

-
ジムニーのミディアムグレーは後悔する?失敗ポイントと対策・口コミを徹底まとめ
「ジムニーのミディアムグレー、かっこいいけど飽きないかな?」 「地味すぎて、商用車っぽく見えたりしな ...
続きを見る
第5位:ホンダ N-ONE RS

ホンダ・N-ONE RS公式
普段使いしやすいハイトワゴンのスタイルに、スポーティーな走りを融合させたモデル。
特に6速マニュアルトランスミッション搭載車は、FF(前輪駆動)ターボならではの痛快な走りを楽しめます。
- 見た目と走りのギャップが面白い
- 6速MTの設定がある
- 先進安全装備「Honda SENSING」も充実
▼関連記事
-

-
軽自動車でサーキットデビュー!おすすめスポーツカー徹底比較
「サーキットを走ってみたいけど、スポーツカーは高くて手が出せない…」 「軽自動車でサーキット走行なん ...
続きを見る
トヨタ・マツダ・レクサスの軽自動車スポーツモデルは?
「トヨタやマツダ、レクサスには軽のスポーツカーはないの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
2025年現在、マツダとレクサスは軽自動車を自社生産しておらず、スポーツモデルも存在しません。
(過去にはマツダがスズキのOEMで「キャロル」などを販売していました)
トヨタは、ダイハツからのOEM供給を受けて「ピクシス」シリーズを販売していますが、純粋なスポーツモデルはありません。
しかし、唯一の例外が「コペン GR SPORT」です。これはダイハツ・コペンをベースに、トヨタのモータースポーツ部門である「TOYOTA GAZOO Racing」が足回りなどを専用チューニングしたモデル。
より引き締まった乗り味と高い操縦安定性を実現しており、トヨタのディーラーで購入できる軽スポーツとして貴重な存在です。
▼関連記事
【2026年生産終了】コペンGRスポーツは後悔する?失敗しない購入ポイント
-

-
【2026年生産終了】コペンGRスポーツは後悔する?失敗しない購入ポイント
「街で見かけるコペンGRスポーツ、あの引き締まったデザインが最高にかっこいい!」 「一度は乗ってみた ...
続きを見る
チューニング可能な軽自動車人気モデル一覧!メーカー別に徹底比較

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
チューニングベースとなる軽自動車を探すなら、メーカーごとの特徴を知っておくと選びやすくなります。
特に、スポーツモデルやカスタムパーツが豊富なのはスズキ、ホンダ、ダイハツの3社です。
- スズキ
アルトワークスやジムニーに代表されるように、古くから軽スポーツやオフロードの分野に強いメーカーです。
エンジンチューニングから足回り、外装まで、膨大な数のアフターパーツが存在し、自分好みのカスタムをとことん追求できます。
- ホンダ
S660やN-ONE RSなど、走りの質にこだわったモデルを多くラインナップ。エンジン技術に定評があり、ノーマルでも高回転まで気持ちよく回るエンジンが魅力です。
操る楽しさを重視するユーザーから高い支持を得ています。
- ダイハツ
コペンという唯一無二の軽オープンカーを持つのが最大の強み。エンジンはスズキやホンダに比べてマイルドな特性ですが、その分扱いやすく、幅広いユーザーに支持されています。
カスタムの方向性も、走りだけでなくドレスアップも人気です。
これらのメーカーの公式サイトでは、ターボ搭載車のラインナップやスペックを簡単に比較できます。
自分のやりたいカスタムの方向性と、各メーカー・車種の得意分野を照らし合わせながら、最適な一台を見つけるのが成功の秘訣です。
▼各メーカー公式サイトリンクまとめ
スズキ「アルトワークス」とホンダ「S660」を馬力や性能で比較!
軽スポーツの双璧とも言える「アルトワークス」と「S660」。
どちらも64馬力という自主規制値いっぱいのパワーを発揮しますが、そのキャラクターは大きく異なります。
| 項目 | スズキ アルトワークス | ホンダ S660 |
|---|---|---|
| コンセプト | 実用性も兼ね備えたホットハッチ | 走りに特化したピュアスポーツ |
| 駆動方式 | FF / 4WD | MR(ミッドシップ) |
| 乗車定員 | 4名 | 2名 |
| 車両重量 | 670kg〜(非常に軽量) | 830kg〜 |
| 走りの特徴 | 軽量ボディを活かした鋭い加速 | コーナーでの高い安定性と回頭性 |
| おすすめな人 | 日常の足としても使いつつ、キビキビした走りを楽しみたい人 | とにかく運転そのものを楽しみたい、純粋な走り好き |
アルトワークスは、その軽さを武器にした瞬発力が魅力。街乗りでのストップ&ゴーも得意で、峠道ではひらりひらりとコーナーをクリアしていきます。4人乗れる実用性も大きなポイントです。
一方のS660は、軽自動車とは思えない低いドライビングポジションと、背後から聞こえるエンジンサウンドが気分を高揚させます。
重心が低く、まるで地面に張り付くようなコーナリング感覚は、S660でしか味わえません。
どちらを選ぶかは、あなたが車に何を求めるか次第。ぜひ中古車販売店などで実車を見比べて、その違いを体感してみてください。
▼関連記事
マニュアルモード付きAT軽自動車まとめ!メリット・走行性能・おすすめ車種を徹底解説
-

-
マニュアルモード付きAT軽自動車まとめ!メリット・走行性能・おすすめ車種を徹底解説
「AT車の運転のしやすさは魅力だけど、MT車のような自分でギアを操る楽しさも捨てがたい…」 「軽自動 ...
続きを見る
ダイハツ・コペンの中古車はチューニングベースに最適な理由とは?

ダイハツ・コペン(初代)(ダイハツ認定中古車公式情報サイトからの引用)
ダイハツ・コペンがチューニングベースとして人気なのには、いくつかの理由があります。
- 豊富な中古車と手頃な価格帯
初代から現行モデルまで、長年にわたり販売されているため中古車のタマ数が豊富です。
年式や走行距離によっては、かなり手頃な価格で手に入れることができ、その分をカスタム費用に回すことができます。
- アフターパーツの多さ
エンジン系、足回り、内外装に至るまで、非常に多くのカスタムパーツが様々なメーカーから販売されています。
自分の理想に合わせて、少しずつ育てていく楽しみがあります。特に外装パーツが豊富で、見た目の印象を大きく変えることも可能です。
- 素直で扱いやすい走行性能
FF駆動で挙動が穏やかなため、運転に自信がない人でも安心してスポーツ走行の基本を学べます。
エンジンもマイルドな特性なので、チューニングによるパワーの変化を体感しやすいというメリットもあります。
- オープンボディの開放感
何と言っても最大の魅力は、気軽にオープンエアドライブが楽しめること。
チューニングでパワーアップしたエンジン音と風を感じながら走る爽快感は、他の軽自動車では味わえません。
これらの理由から、コペンは「初めてのスポーツカー」や「カスタム入門」に最適な一台と言えるでしょう。
まずは修復歴のない程度の良い中古車を探し、そこから自分色に染めていくのがおすすめです。
▼関連記事
コペン エクスプレイは本当にダサい?生産終了で希少価値急上昇!今こそ狙い目?
-

-
コペン エクスプレイは本当にダサい?生産終了で希少価値急上昇!今こそ狙い目?
「個性的なデザインのコペン エクスプレイが気になるけど、ネットで『ダサい』という声もあって不安・・・ ...
続きを見る
旧型コペン(L880K)は本当に今が買い時?値上がりの理由と今後の相場は?
-

-
旧型コペン(L880K)は本当に今が買い時?値上がりの理由と今後の相場は?
「最近、街で見かける初代コペン(L880K)が気になっているけど、中古車サイトを見たら思ったより価格 ...
続きを見る
馬力を上げた軽自動車の中古車購入はおトク?注意すべきポイント解説

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
すでに馬力アップの改造が施された中古車は、一から自分でカスタムする手間や費用が省けるため、一見するとおトクに思えます。
しかし、購入にはいくつかの注意が必要です。
最大の懸念点は、「どのような改造が、どのようなレベルで行われたか分からない」ことです。
知識の浅い素人が行った不適切な改造や、過度なチューニングによってエンジンや車体に大きな負担がかかっている可能性があります。
購入後にすぐ故障したり、実は車検に通らない違法改造車だったりするリスクもゼロではありません。
改造済み中古車を選ぶ際は、以下のポイントを必ずチェックしましょう。
- 整備記録簿(メンテナンスノート)の有無
いつ、どこで、どのような整備や改造が行われたかが分かる重要な書類です。記録がしっかり残っている車は、素性がはっきりしており安心感が高いです。
- チューニング内容の詳細な確認
どこのメーカーの、どのパーツが使われているか、ECUのセッティングはどうなっているかなど、販売店のスタッフに詳しく質問しましょう。
明確に答えられない場合は要注意です。
- エンジンルームや下回りのチェック
オイル漏れや不自然な配線、サビなどがないか、自分の目で確認しましょう。エンジンをかけてみて、異音や白煙が出ていないかも重要なチェックポイントです。
- 試乗
実際に運転してみて、まっすぐ走るか、ブレーキはしっかり効くか、ミッションの入りはスムーズかなどを体感することが最も重要です。
信頼できる中古車販売店を選び、これらのポイントをしっかり確認することが、改造済み中古車選びで失敗しないための鉄則です。
▼お近くのガリバーで中古車を探してみる(中古車・PR)
▼関連記事
ガリバーはやばい?やめとけと言われる理由と中古車購入で失敗しない対策
-

-
ガリバーはやばい?やめとけと言われる理由と中古車購入で失敗しない対策
「あ、このN-BOXいいな!でも販売店がガリバーか…」 中古車サイトを見ていて、そんな ...
続きを見る
中古車選びの基本的なポイントや注意点については、「後悔しない中古軽自動車の選び方と人気おすすめ車種を徹底解説」の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
-

-
後悔しない中古軽自動車の選び方と人気おすすめ車種を徹底解説
「中古で軽自動車を買いたいけど、どんな点に注意すればいいんだろう…」 「買ってから後悔するような失敗 ...
続きを見る
もし中古車でMTモデルを探すなら、「初めてでも安心!失敗しない軽自動車マニュアル中古車の選び方とおすすめ車種」の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
-

-
初めてでも安心!失敗しない軽自動車マニュアル中古車の選び方とおすすめ車種
「運転が楽しいマニュアルの軽自動車に乗りたいけど、中古で探すのは少し不安…」 「どんな車種があって、 ...
続きを見る
▼関連記事
軽自動車の中古はやめたほうがいい?買う前に確認すべき重要ポイント
-

-
軽自動車の中古はやめたほうがいい?買う前に確認すべき重要ポイント
軽自動車の中古は、価格が魅力ですが、自動車としての走行距離や整備履歴をしっかり確認しないと、エンジン ...
続きを見る
軽自動車の中古市場で見るべき走行距離や搭載エンジンのポイント
パワフルな軽自動車を中古で探すなら、走行距離とエンジンの状態は特に念入りにチェックしたいポイントです。
走行距離は、一つの目安として「10万km」を意識すると良いでしょう。しかし、重要なのは距離そのものよりも「メンテナンスの履歴」です。
たとえ走行距離が短くても、オイル交換などの基本的なメンテナンスを怠ってきた車は、エンジンの状態が悪い可能性があります。
逆に10万kmを超えていても、定期的にしっかりメンテナンスされてきた車なら、まだまだ元気に走ってくれます。
搭載エンジンで特に注意したいのが「ターボ車」です。ターボチャージャーはエンジンの排気ガスを利用して高速で回転するため、常に高温・高負荷にさらされています。
そのため、エンジンオイルの管理が非常に重要になります。
- オイル交換の頻度
ターボ車は3,000km〜5,000km、または半年に一度のオイル交換が推奨されます。整備記録簿で、このサイクルが守られているかを確認しましょう。
- オイル漏れや滲み
エンジン周りを見て、オイルが漏れたり滲んだりしている跡がないかチェックします。
- 異音や白煙
エンジン始動時やアイドリング中、加速時に「ヒューン」「カラカラ」といった異音がしないか、マフラーから白い煙が出ていないかを確認しましょう。
白煙はターボが故障しているサイン(オイル下がり・オイル上がり)の可能性があります。
購入前の試乗は必須です。可能であれば、専門知識のある友人に同行してもらうか、信頼できる販売店で購入することをおすすめします。
▼関連記事
軽自動車が10万キロ超えたら?寿命と故障リスクと購入時の注意点を解説
-

-
軽自動車が10万キロ超えたらどうなる?維持費・故障リスク・買い替え目安まとめ
「愛車の軽自動車、走行距離が10万キロを超えそう…」 「10万キロ超えたら、もう寿命なのかな?」 「 ...
続きを見る
届出済未使用車は馬力アップ可能?購入前に確認すべき規約と現実
「届出済未使用車」とは、一度ナンバー登録されたものの、実際には公道をほとんど走行していない新車同様の車のことです。
新車より安く手に入るため人気がありますが、これをベースに馬力アップ改造を検討する際には注意が必要です。
結論から言うと、届出済未使用車でも馬力アップ改造は可能ですが、メーカーの保証が受けられなくなる可能性が非常に高いです。
自動車メーカーが提供する新車保証は、メーカーが定めた仕様通りに使用されることが前提です。エンジンやECUに手を入れるような改造は「不正改造」とみなされ、保証の対象外となります。
万が一、改造が原因でエンジンが故障しても、修理費用はすべて自己負担になってしまいます。また、ディーラーによっては改造車の入庫自体を断られるケースもあります。
「どうしてもパワーアップしたい」という強い希望があるなら、保証が切れるのを待つか、保証がなくなることを覚悟の上で行うしかありません。
しかし、多くの場合、最初からターボが搭載されているグレードを選ぶ方が、コスト的にも安全性の面でもはるかに賢明な選択と言えるでしょう。
馬力64馬力を超えた軽自動車の新車・中古車選びで気をつけるべきこと

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
これまでの内容を踏まえ、64馬力を超える(または超えるように改造された)軽自動車を選ぶ際の注意点を改めて整理します。
新車の場合、基本的に国内メーカーで64馬力を超える新車はありません。もし海外メーカーの小型車などで規格内に収まるモデルがあれば、それは軽自動車ではなく小型車として登録されます。
トヨタの「コペン GR SPORT」のように、メーカー自身がチューニングを施したモデルは、走りも保証も安心できる良い選択肢です。
最も注意が必要なのが中古車です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改造内容の把握 | どんなパーツで、誰が、どのように改造したのかを徹底的に確認する。 |
| 車両状態の見極め | エンジン、駆動系、足回り、ボディの状態をプロの目でチェックしてもらうのが理想。 |
| 車検への適合性 | その状態で本当に次の車検に通るのか、販売店に確認する。 |
| 購入後のリスク | 改造車はノーマル車に比べて故障のリスクが高いことを理解し、ある程度の維持費を覚悟しておく。 |
「安くて速い」という魅力的な響きの裏には、相応のリスクが潜んでいることを忘れてはいけません。
▼関連記事
【2026年生産終了】コペンGRスポーツは後悔する?失敗しない購入ポイント
-

-
【2026年生産終了】コペンGRスポーツは後悔する?失敗しない購入ポイント
「街で見かけるコペンGRスポーツ、あの引き締まったデザインが最高にかっこいい!」 「一度は乗ってみた ...
続きを見る
64馬力規制前の魅力的な軽スポーツカー!日産・スバル・三菱の名車紹介
64馬力自主規制が始まる前後の1990年代初頭は、個性的な軽スポーツカーが数多く生まれた黄金時代でした。
中古でしか手に入らないこれらの名車は、今なお多くのファンを魅了しています。
日産 フィガロ (1991年)

日産・フィガロ(グーネット モデル・グレード別カタログ情報からの引用)
小型乗用車の区分ですが、レトロで愛らしいデザインが特徴のパイクカーシリーズの一台。ターボエンジンを搭載し、見た目によらずキビキビと走ります。
オープンにできるルーフも魅力で、ファッション性の高い一台です。
スバル ヴィヴィオ RX-R (1992年)

スバル・ヴィヴィオ(VIVIO)RX-R(グーネット モデル・グレード別カタログ情報からの引用)
スーパーチャージャー付きの4気筒エンジンを搭載し、自主規制値いっぱいの64馬力。
ラリーで活躍したノウハウが注ぎ込まれ、その走りは「軽じゃない」とまで言われました。
今でも根強いファンを持つ伝説的なホットハッチです。
三菱 パジェロミニ (1994年)

三菱・パジェロミニ(2代目)(グーネット モデル・グレード別カタログ情報からの引用)
大人気だった「パジェロ」をそのまま軽サイズにしたようなデザインで大ヒット。見た目だけでなく、本格的なラダーフレームと4WDシステムを備え、悪路走破性も非常に高いモデルでした。
ターボモデルは街乗りもパワフルにこなします。
これらの車は年式が古いため、購入後のメンテナンスは必須ですが、現代の車にはない独特の魅力と運転する楽しさに溢れています。
▼関連記事
-

-
三菱パジェロミニを買って後悔する人が語る不満ポイント大全
「個性的なデザインのパジェロミニ、中古で安く買えるし魅力的だな。でも、古い軽自動車だから買ってから後 ...
続きを見る
軽自動車で64馬力規制以上の買取査定は実際どうなる?高く売るコツとは
馬力アップした愛車を手放す際、「改造はプラス査定になるのか?」は気になるところです。
これはケースバイケースで、プラスになることもあれば、逆にマイナスになることもあります。
【プラス査定が期待できる改造】
- 有名ブランドの高品質なパーツ(ホイール、マフラー、足回りなど)
- きちんと構造変更検査を受けており、合法的な状態であること
- 車種のファンに人気の定番カスタムが施されていること
【マイナス査定になりやすい改造】
- 車検に通らない違法改造(触媒ストレート、過度なオーバーフェンダーなど)
- DIYによる質の低い改造
- 元の状態に戻せないような過度な改造
高く売るコツは、改造車の価値を正しく評価してくれる買取店に査定を依頼することです。
一般的な中古車買取店では改造車は敬遠されがちですが、スポーツカーやカスタムカーを専門に扱う買取店なら、パーツの価値やカスタム内容を評価して高値を付けてくれる可能性があります。
査定に出す際は、ノーマルパーツが残っていれば一緒に提出すると、さらに評価が上がりやすくなります。
▼カーセンサーで買取査定してみる(車買取査定・PR)
▼関連記事
カーセンサー一括査定の評判は本当?口コミ・電話対策・注意点を解説
-

-
カーセンサー一括査定の評判は本当?口コミ・電話対策・注意点を解説
「愛車を少しでも高く売りたいけれど、カーセンサーの一括査定って実際どうなの?」 「『カーセンサー 評 ...
続きを見る
地域別に異なる車検対応サービスと軽自動車の馬力規制への対策
基本的に、車検の保安基準は全国どこでも同じです。しかし、検査を行う陸運支局や軽自動車検査協会、あるいは民間の指定工場(ディーラーや車検専門店など)の検査員の判断によって、グレーゾーンの解釈に若干の差が出ることがあると言われています。
特に、カスタムされた軽自動車の場合、その対応は工場によって様々です。
- ディーラー
メーカーの基準を重視するため、少しでも純正と異なる点があると厳しく見られがちです。
改造車の車検は断られることもあります。
- 車検専門フランチャイズ
多くの台数を効率よくこなすため、規格外の車や判断が難しい改造車は敬遠される傾向があります。
- チューニングショップ・カスタムショップ
改造に関する知識が豊富で、保安基準に適合させるためのノウハウを持っています。
構造変更検査などの手続きにも慣れているため、最も頼りになる存在です。
馬力アップした軽自動車の車検で困ったら、近所のチューニングショップや、カスタムカーの車検実績が豊富な整備工場に相談するのが一番の近道です。
インターネットの口コミや評判を参考に、信頼できるお店を探してみましょう。
▼【楽天Car車検】で近所の安いお店を探す(車検・PR)
馬力アップした軽自動車の保険や安全性、税金への影響を正しく知る

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
軽自動車を馬力アップすると、走りだけでなく、保険や安全性、税金といった維持の側面にも影響が及びます。
これらの変化を正しく理解しておくことは、安心してカーライフを楽しむために非常に重要です。
【保険への影響】
エンジンチューニングなどの改造を行った場合、保険会社への「告知義務」が発生します。
これを怠ると、万が一事故を起こした際に保険金が支払われない可能性があります。
改造内容によっては保険料が割増になったり、加入を断られたりするケースもあります。
【安全性への影響】
64馬力という出力は、軽自動車の小さなボディやブレーキ性能とのバランスを考慮した上での数値でもあります。
パワーだけを大幅に上げると、
- スピードが出すぎてカーブを曲がりきれない
- ブレーキが効かずに追突してしまう
といったリスクが高まります。パワーアップするなら、それに見合ったブレーキの強化や、高性能なタイヤへの交換が不可欠です。
【税金への影響】
排気量を上げたり、オーバーフェンダーを取り付けたりして軽自動車の規格を超えた場合、「構造変更」を行い普通車として登録することになります。
その場合、毎年の自動車税は軽自動車税ではなく、排気量に応じた普通車の税額になるため、負担は大きく増加します。
軽自動車の馬力アップが保険料や維持費に与える影響を徹底解説
馬力アップが維持費に与える影響を、もう少し具体的に見てみましょう。
【保険料】
保険会社は、車種や型式ごとに事故率を算出し、保険料を決定しています。エンジンを改造して馬力を上げた車は、事故のリスクが高いと判断され、保険料が割増になるのが一般的です。
改造内容を正直に申告した上で、複数の保険会社に見積もりを依頼し、加入できる保険を探す必要があります。
▼【インズウェブ】自動車保険一括見積もり(自動車保険・PR)
▼関連記事
インズウェブ自動車保険の口コミ・評判は?一括見積もりのメリットと注意点を徹底解説
-

-
インズウェブ自動車保険の口コミ・評判は?一括見積もりのメリットと注意点を徹底解説
「自動車保険の更新時期が近づいてきたけれど、今の保険料は高すぎる気がする…」 「インズウェブで一括見 ...
続きを見る
【その他の維持費】
- 燃費の悪化
パワーを上げれば、その分ガソリンの消費量も増えるのが普通です。
ガソリン代の負担は確実に増えると考えましょう。
- メンテナンス費用
高性能なエンジンは、より高品質なエンジンオイルを、より短いサイクルで交換する必要があります。
また、パワーが上がれば他の部品への負担も増え、故障のリスクや消耗品の交換頻度も高まります。
パワーを手に入れることは、これらの維持費の増加と引き換えであることを理解しておく必要があります。
馬力64馬力以上の軽自動車は本当に危険?安全性とシートの重要性
「64馬力以上の軽自動車は危険」と一概に言うことはできません。重要なのは、「パワーと安全性のバランスが取れているか」です。
ノーマルの軽自動車は、64馬力のパワーに対して十分な安全マージンが確保されています。
しかし、これを100馬力、120馬力と上げていくのであれば、他の部分も相応に強化しなければ、非常に危険な乗り物になってしまいます。
特に重要なのが、ブレーキ、タイヤ、サスペンションといった「止まる」「曲がる」を司る足回りの部分です。そして、意外と見落とされがちなのが「シート」です。
ノーマルのシートは、快適性を重視しているため、スポーツ走行時の横G(遠心力)に対して体を支える能力は高くありません。
体が左右に振られてしまうと、正確なハンドル操作やペダル操作が困難になります。
体をしっかりとホールドしてくれる「バケットシート」に交換することで、運転姿勢が安定し、車との一体感が高まります。
これにより、車の挙動が掴みやすくなり、結果として安全運転に繋がるのです。
パワーアップを考えるなら、まずドライバーが座るシートの重要性にも目を向けてみてください。
まとめ:軽自動車64馬力規制と車検問題を正しく理解して安全で快適なカーライフを!

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
今回は、軽自動車の64馬力規制と、パワーアップ改造、そして車検の問題について詳しく解説してきました。
最後に、今回の内容をまとめておきましょう。
【今回のまとめ】
- 64馬力規制は法律ではなく、安全性を目的としたメーカーの「自主規制」である。
- 64馬力を超える改造をしても、保安基準を満たし、軽自動車の規格(寸法・排気量)内であれば車検を通すことは可能。
- 規格を超える改造(排気量アップやオーバーフェンダーなど)は、「構造変更検査」を受けて普通車として登録し直す必要がある。
- パワーアップする際は、ブレーキやタイヤなど足回りの強化もセットで行い、安全性とのバランスを取ることが最も重要。
- 改造を行った場合は保険会社への告知義務があり、保険料や税金などの維持費が増加する可能性がある。
軽自動車のパワーに物足りなさを感じる気持ちは、車好きなら誰しもが抱く自然な感情です。
しかし、ルールを無視した改造は、あなた自身だけでなく、周りの人々を危険に晒すことにもなりかねません。
この記事で得た知識を元に、法律やルールを守りながら、安全に、そして賢く、あなただけの理想の軽自動車を追求してみてください。
信頼できるプロの力を借りながら、合法的な範囲で愛車のポテンシャルを引き出すことができれば、あなたのカーライフはもっと豊かで楽しいものになるはずです。