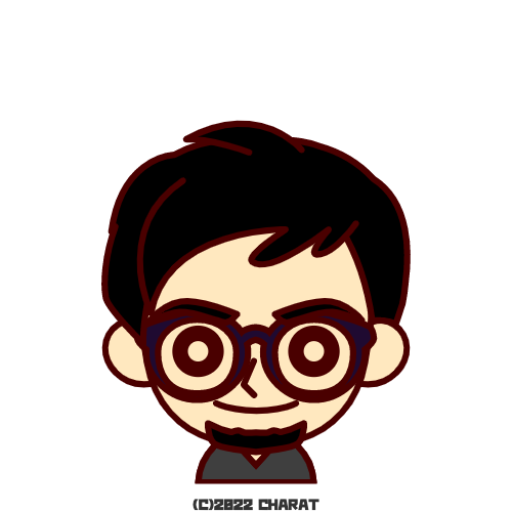「軽自動車」って普段何気なく呼んでいるけれど、そういえば「正式名称」はなんだろう?
と疑問に思ったことはありませんか。
車検証を見たときに「軽四輪乗用自動車」と書かれていて、どっちが本当の名前?
と混乱してしまう方もいらっしゃるかもしれませんね。
また、これから軽自動車の購入を考えている方にとっては、普通車と何が違うのか、定義や基準もしっかり知っておきたいところでしょう。
この記事では、軽自動車の正式名称について徹底的にお答えします。
この記事でわかること
- 軽自動車の正式名称と、その由来や歴史
- 法律で定められた軽自動車の明確な定義(規格・基準)
- 普通車や小型乗用車との具体的な違い(税金、ナンバープレートなど)
- 知っておくと役立つ軽自動車の種類やメンテナンスの知識
読み終わる頃には、軽自動車に関する「そうだったのか!」という発見と共に、あなたのカーライフがより豊かなものになるはずです。
ぜひ最後までお付き合いください。
軽自動車の正式名称とは?基本から押さえる軽自動車の定義と特徴

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
私たちが日常的に使っている「軽自動車」という呼び名。
実はこれ、法律(道路運送車両法)で定められた車両区分を指す正式な名称(区分名)なんです。
時々、車検証(自動車検査証)の「用途車種」欄に「軽四輪乗用自動車」や「軽四輪貨物自動車」といった記載があるため、「これが正式名称?」と迷われる方もいます。
これは、大きな「軽自動車」という区分の中で、その車が「人を乗せるため(乗用)」なのか「荷物を運ぶため(貨物)」なのか、さらに細かく分類している用途車種名と呼ばれるものです。
ですから、「軽自動車の正式名称は?」と聞かれたら、答えは「軽自動車」であり、車検証に記載されているのは「用途車種名(軽自動車の中での具体的な分類)」と理解しておくとスッキリしますね。
この「軽自動車」という区分には、非常に厳格な「定義」があります。
それは、日本の法律によって定められた特定の規格(サイズや排気量)を満たす自動車のみが名乗れる称号のようなもの。
この規格こそが、軽自動車の最大の特徴であり、私たちが受ける税金の優遇など、様々なメリットの源泉となっているのです。
次からは、その由来や具体的な基準について、さらに詳しく掘り下げていきましょう。
軽自動車の正式名称の由来と歴史を徹底解説!なぜ“軽”自動車になったのか
では、なぜ「“軽”自動車」と呼ばれるようになったのでしょうか。
その由来は、文字通り「規格が小さい(軽い)」こと、そしてそれに伴い「税金などの負担が軽い」ことから来ています。
軽自動車の歴史は、第二次世界大戦後の復興期まで遡ります。
当時、多くの国民にとって自動車は高嶺の花でした。
そこで、もっと手軽に人々が移動手段を持てるようにと、国策として安価で維持費の安い自動車の規格が考案されました。
これが軽自動車の始まりです。
最初の規格は1949年(昭和24年)に定められ、当時はなんと排気量150cc以下(四輪車の場合)という、現在のバイクのような非常に小さなものでした。
その後、国民の所得向上や技術の進歩に合わせて、規格は360cc、550ccと段階的に拡大され、1998年(平成10年)に現在まで続く「排気量660cc以下」という規格になりました。
このように、軽自動車は「国民の足」として手軽に乗れることを目指して誕生した背景があり、その「手軽さ=軽さ」が「軽自動車」という正式名称の由来となっているのです。
軽自動車の概要と基準要件:自動車検査や免許の基礎知識も紹介
「軽自動車」と正式に認められるためには、国の定める以下の基準(規格要件)をすべて満たしている必要があります。
これは「道路運送車両法」という法律で厳密に定められています。
【軽自動車の規格(2025年現在)】
- 長さ: 3.40m 以下
- 幅: 1.48m 以下
- 高さ: 2.00m 以下
- 排気量: 660cc 以下
この4つの条件をすべてクリアした四輪車(および三輪車)が「軽自動車」と呼ばれます。
この小さなボディサイズこそが、狭い日本の道でも運転しやすい小回りの良さを生み出しています。
- 自動車検査(車検)について
軽自動車も普通車と同様に、定期的な車検(自動車検査登録制度)を受ける義務があります。
ただし、普通車が「運輸支局」で検査を受けるのに対し、軽自動車は「軽自動車検査協会」という専門の機関が管轄しています。
新車登録時は3年後、以降は2年ごとに車検を受ける点は普通車(乗用車)と同じです。
▼関連記事
軽自動車の車検はいくらかかった?実際の費用・内訳・相場を徹底解説
-

-
軽自動車の車検はいくらかかった?実際の費用・内訳・相場を徹底解説
「もうすぐ初めての車検だけど、いくらかかるか不安」 「ディーラーから届いた見積もりが10万円を超えて ...
続きを見る
軽自動車7年目の車検費用はなぜ高い?相場・内訳・安くするコツ
-

-
軽自動車7年目の車検費用はなぜ高い?相場・内訳・安くするコツ
「7年目の軽自動車の車検、見積もりを見たら思ったより高くて驚いた…」 「3回目となる今回の車検、いっ ...
続きを見る
- 運転免許について
軽自動車の運転に必要な免許は、「普通自動車免許(普通免許)」です。
「軽自動車専用免許」というものは存在しません。AT(オートマチック)限定の普通免許でも、もちろん軽自動車のAT車を運転することができます。
これから免許を取得する方も、すでに普通免許をお持ちの方も、特別な手続きなく運転できるのが軽自動車の手軽さの一つですね。
ただし、運転する際は万が一の事故に備え、自動車保険への加入が不可欠です。
複数の保険会社を比較検討できる自動車保険一括見積もりサービス「インズウェブ」などを利用して、ご自身に合ったプランを選んでおくと安心です。
▼自動車保険一括見積もりサービス「インズウェブ」で保険料を比較する(自動車保険・PR)
▼関連記事
インズウェブ自動車保険の口コミ・評判は?一括見積もりのメリットと注意点を徹底解説
-

-
インズウェブ自動車保険の口コミ・評判は?一括見積もりのメリットと注意点を徹底解説
「自動車保険の更新時期が近づいてきたけれど、今の保険料は高すぎる気がする…」 「インズウェブで一括見 ...
続きを見る
軽自動車が他の車種と何が違う?小型乗用車との規格・税金の違い

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
軽自動車の正式名称と定義がわかったところで、次に気になるのが「他の車と具体的に何が違うの?」という点ですよね。
特に、見た目がコンパクトな「小型乗用車(通称:5ナンバー車)」との違いは分かりにくいかもしれません。
最も大きな違いは、先ほど紹介した「規格」と、それに伴う「税金」です。
【規格(サイズ・排気量)の違い】
| 車種区分 | 排気量 | 長さ | 幅 | 高さ |
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 660cc以下 | 3.40m以下 | 1.48m以下 | 2.00m以下 |
| 小型乗用車 (5ナンバー) | 2,000cc以下 | 4.70m以下 | 1.70m以下 | 2.00m以下 |
| 普通乗用車 (3ナンバー) | 上記を超えるもの | 上記を超えるもの | 上記を超えるもの | 上記を超えるもの |
※小型乗用車は、排気量・長さ・幅・高さの「いずれか一つでも」軽自動車の規格を超え、かつ「すべてが」小型乗用車の規格内に収まる車を指します。
【税金の違い(年間)】
| 税金の種類 | 軽自動車(自家用乗用) | 小型/普通乗用車(自家用) |
|---|---|---|
| 軽自動車税(種別割) | 10,800円 (標準) | - |
| 自動車税(種別割) | - | 25,000円~ (排気量1,000cc以下の場合) |
| 自動車重量税 | 年3,300円 (エコカー減税適用なし・車検時2年分) | 年8,200円~ (~1t・エコカー減税適用なし・車検時2年分) |
※税額は2026年現在の標準的な例です。新規登録時期やエコカー減税の適用によって異なります。
このように、軽自動車は規格が小さい分、税金が大幅に安く設定されています。
これが「維持費が安い」と言われる最大の理由です。
他にも、高速道路の通行料金が普通車よりも安く(約2割引)設定されているなど、経済的なメリットは大きいですね。
▼関連記事
-

-
維持費が変わらないって本当?軽自動車とコンパクトカーの実態
「軽自動車は維持費が安いって聞くけど、最近のコンパクトカーとあまり変わらないって本当?」 「結局、自 ...
続きを見る
軽自動車と普通車の高速料金はどれだけ違う?おすすめの選び方も解説
-

-
軽自動車と普通車の高速料金はどれだけ違う?おすすめの選び方も解説
「軽自動車は維持費が安いって聞くけど、高速道路の料金も安いのかな?」 「普通車と比べて、実際にどれく ...
続きを見る
軽乗用車・四輪貨物車・特種用途車など種類別の特徴と用途
「軽自動車」という大きな枠の中にも、その使い方によっていくつかの種類(用途車種)があります。
これはナンバープレートの「分類番号(地名の横にある数字)」で見分けることができます。
軽乗用車(分類番号:5ナンバー、7ナンバー)
- 主に人を乗せることを目的とした軽自動車です。
- ホンダのN-BOXのようなハイトワゴン、スズキのハスラーのようなSUVタイプ、ダイハツのコペンのようなスポーツカーまで、多様なモデルがあります。
- 私たちの生活に最も身近なタイプで、車検証には「軽四輪乗用自動車」と記載されます。
- 定員は最大4名です。
軽四輪貨物車(分類番号:4ナンバー、6ナンバー)
- 主に荷物を運ぶことを目的とした軽自動車です。
- スズキのエブリイバンやダイハツのハイゼットトラックなどが代表的です。
- 乗車スペースよりも荷室スペースが広く設計されているのが特徴です。
- 個人事業主の方や、アウトドア・車中泊のベース車としても人気があります。
- 車検は新車登録時から2年ごと(乗用は初回3年)となります。
特種用途車(分類番号:8ナンバー)
- 特定の用途に使われるための特別な設備を持つ軽自動車です。
- 軽キャンピングカー、パトカー、消防車、タンクローリーなどがこれにあたります。
- 税金や車検の条件が他のタイプと異なる場合があります。
このように、同じ軽自動車の規格内でも、目的に合わせて様々なタイプが作られています。
ご自身のライフスタイルに合った一台を見つけるのも、軽自動車選びの楽しさの一つですね。
▼関連記事
軽自動車の4ナンバーと5ナンバーはどちらが安い?維持費を徹底比較して選び方まで解説
-

-
軽自動車の4ナンバーと5ナンバーはどちらが安い?維持費を徹底比較して選び方まで解説
「軽自動車を買いたいけれど、維持費はできるだけ安く抑えたい」 「4ナンバーと5ナンバーってよく聞くけ ...
続きを見る
軽自動車と普通自動車・小型自動車の比較ポイントまとめ
ここまでの内容を、比較ポイントとしてまとめてみましょう。
| 比較ポイント | 軽自動車 | 小型自動車(5ナンバーまたは7ナンバー) | 普通自動車(3ナンバー) |
|---|---|---|---|
| 正式名称(区分) | 軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 |
| 規格 (最大) | 660cc / 長3.4m / 幅1.48m / 高2.0m | 2,000cc / 長4.7m / 幅1.7m / 高2.0m | 小型自動車の基準を1つでも超える項目ある |
| ナンバープレート | 黄色地 (自家用) / 黒色地 (事業用) | 白色地 (自家用) / 緑色地 (事業用) | 同左 |
| 乗車定員 (最大) | 4名 | 規格による (多くは5名~) | 規格による |
| 税金 (自動車税/軽自動車税) | 安い (年10,800円~) | 排気量に応じる (年25,000円~) | 排気量に応じる |
| 高速道路料金 | 安い (普通車の約2割引) | 普通車料金 | 普通車料金 |
| 主なメリット | 維持費が安い、小回りが利く、運転しやすい | 軽よりパワー・安定性あり、5人乗りも | パワー、安定性、安全性、選択肢の幅 |
| 主なデメリット | 乗車定員4名、パワー不足を感じることも | 軽より維持費が高い | 維持費が高い、狭い道で運転しにくい |
(※「小型自動車」「普通自動車」は、道路運送車両法における区分であり、「小型乗用車」「普通乗用車」はナンバー(分類番号)による区分けです。ここでは分かりやすさを優先しています。)
表で比べると、軽自動車の経済的なメリットとコンパクトさが際立ちますね。
一方で、乗車人数や長距離運転の快適性では小型車や普通車に軍配が上がる面もあります。
どちらが良い・悪いではなく、ご自身の使い方に合っているかが大切です。
軽自動車ナンバープレートの正式名称や標識の意味・文字のルール

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
軽自動車を見分ける最も簡単な方法の一つが、ナンバープレートの色です。
- 自家用: 黄色地に黒文字
- 事業用(配送業など): 黒地に黄色文字
この黄色いナンバープレートは軽自動車の象徴とも言えますね。
ただし近年は、ラグビーワールドカップやオリンピックの特別仕様、ご当地ナンバーなどで、普通車と同じ白色の軽自動車ナンバープレートも交付されています。
(出典:国土交通省「図柄入りナンバープレート」より)
ちなみに、普通車などのナンバープレートの正式名称は「自動車登録番号標」ですが、軽自動車のものは「車両番号標」といいます。
これは、普通車が「登録」されるのに対し、軽自動車は「届出」されるという法律上の手続きの違いに基づいています。
ナンバープレートに書かれている文字や数字にも、すべて意味があります。
- 地名: 使用の本拠の位置(管轄の検査協会)
- 分類番号: 車両の種類(580~599なら軽乗用車、480~499なら軽貨物車など)
- ひらがな: 用途(「わ」「れ」はレンタカーなど)
- 一連指定番号: 4桁の数字(希望ナンバーも可能)
これらのルールを知っておくと、街で見かける車がどんな車なのか、少し分かって面白いかもしれません。
▼関連記事
軽自動車のナンバープレート枠は白で隠す!車検対応フレームの選び方徹底解説
-

-
軽自動車のナンバープレート枠は白で隠す!車検対応フレームの選び方徹底解説
「軽自動車の黄色いナンバープレート、どうも好きになれない…」 「枠だけでも隠してスッキリ見せたいけど ...
続きを見る
軽自動車ナンバープレートの黄色枠を隠すおすすめ方法|車検対応フレーム4選
-

-
軽自動車ナンバープレートの黄色枠を隠すおすすめ方法|車検対応フレーム4選
「軽自動車の黄色いナンバープレート、どうにかならないかな…」 「ボディカラーと合わなくて、少し安っぽ ...
続きを見る
-

-
軽自動車ナンバープレート枠を隠す黒フレームおすすめ5選
「軽自動車の黄色いナンバープレートの枠、どうにかして隠せないかな…」 「黒いフレームでカッコよくした ...
続きを見る
軽自動車の車検・ガソリン使用や月ごとのメンテナンスのポイント
軽自動車は維持費が安いとはいえ、安全に乗り続けるためには定期的なメンテナンスが欠かせません。
- 車検(自動車検査)
先述の通り、軽自動車の車検は「軽自動車検査協会」の管轄で、新車は3年後、以降は2年ごとです。
ディーラーや整備工場、ガソリンスタンドなど、様々な場所で受けることができます。
費用を比較して賢く選びたい方には、「楽天Car車検」のような予約サイトが便利です。
ご近所の車検工場を比較・予約でき、ポイントも貯まるのでお得ですよ。
▼【楽天Car車検】で近所の安いお店を探す(車検・PR)
▼関連記事
楽天Car車検の評判はどう?口コミから分かるメリット・デメリットを徹底解説
-

-
楽天Car車検の評判はどう?口コミから分かるメリット・デメリットを徹底解説
「そろそろ車検の時期だけど、ディーラーは高いし、もう少し費用を抑えたい…」 「楽天Car車検が安いっ ...
続きを見る
- ガソリン
ほとんどの軽自動車は「レギュラーガソリン」仕様です。
一部のターボ車などで「ハイオク指定」の場合もありますが、基本的にはレギュラーで問題ありません。
燃費が良いモデルが多いのも軽自動車の魅力ですね。
▼関連記事
軽自動車の月々のガソリン代はいくら?普通車との違いや節約術まで徹底解説!
-

-
軽自動車の月々のガソリン代はいくら?普通車との違いや節約術まで徹底解説!
「軽自動車って維持費が安いって聞くけど、実際のところ、毎月のガソリン代はいくらかかるんだろう?」 「 ...
続きを見る
- 月ごとのセルフメンテナンス
こうした簡単なチェックを心がけるだけでも、車のコンディションを良好に保ち、急なトラブルを防ぐことにつながります。
- タイヤの空気圧: 燃費や走行安定性に直結します。ガソリンスタンドで簡単にチェックできます。
- エンジンオイル: 定期的な交換が必要です。走行距離や時期(例:半年に1回)を目安に確認・交換しましょう。
- ウォッシャー液: 窓の汚れを落とすために必要です。減っていたら補充しましょう。
▼関連記事
軽自動車のオイル選び!0w20と5w30の意外な落とし穴とは?
-

-
軽自動車のオイル選び!0w20と5w30の意外な落とし穴とは?
「そろそろ軽自動車のオイル交換時期だけど、0w-20と5w-30、どっちを選べばいいんだろう?」 「 ...
続きを見る
エンジンオイルを交換しないとどうなる?放置で起こる症状と修理費を徹底解説
-

-
エンジンオイルを交換しないとどうなる?放置で起こる症状と修理費を徹底解説
「あれ?最後にオイル交換をしたの、いつだっけ…?」 ふと気がついたとき、少し不安になっ ...
続きを見る
軽自動車の免許取得や運転に必要な条件・注意点まとめ
軽自動車の運転に必要なのは「普通自動車免許」のみで、特別な資格は要りません。
AT限定免許でも、現在の軽自動車のほとんどはAT車ですので問題ありません。
ただし、軽自動車ならではの運転時の注意点も知っておきましょう。
- 車体の軽さ
車体が軽いため、強風時(特に高速道路や橋の上)はハンドルが取られやすく感じることがあります。
- パワー感
普通車と比べると、急な上り坂や高速道路での合流時にパワー不足を感じる場合があります。
ターボ搭載モデルなら、この点はかなり解消されます。
- 小回りの良さ
最大のメリットです。狭い道でのすれ違いやUターン、駐車が非常に楽に行えます。
こうした特性を理解して運転することが大切です。
そして、車を運転する上で絶対に忘れてはならないのが自動車保険(任意保険)です。
自賠責保険(強制保険)だけでは、万が一の対人・対物事故の補償は十分ではありません。
自動車保険一括見積もりサービス「インズウェブ」などを活用し、複数の保険会社の見積もりを比較して、ご自身の運転頻度や補償内容に合った保険を必ず選んでください。
▼【インズウェブ】自動車保険一括見積もり(自動車保険・PR)
▼関連記事
インズウェブ自動車保険の口コミ・評判は?一括見積もりのメリットと注意点を徹底解説
-

-
インズウェブ自動車保険の口コミ・評判は?一括見積もりのメリットと注意点を徹底解説
「自動車保険の更新時期が近づいてきたけれど、今の保険料は高すぎる気がする…」 「インズウェブで一括見 ...
続きを見る
また、毎日の通勤や休日のドライブをより楽しくするために、Amazon Audible(オーディブル)で「聴く読書」を楽しむのもおすすめです。
運転中でも耳から情報をインプットでき、時間を有効活用できますよ。
▼【Amazon Audible】で聞く読書を(PR)
私自身も通勤中に活用している耳で聴く読書サービス「Amazon Audible」。
▼関連記事
軽自動車にターボなしは後悔する?高速道路での注意点と選び方を徹底解説
-

-
軽自動車にターボなしは後悔する?高速道路での注意点と選び方を徹底解説
「軽自動車が欲しいけど、ターボなしだと高速道路でしんどいのかな…」 「街乗りメインだけど、たまに高速 ...
続きを見る
軽自動車の制度改正と歴史的背景|なぜ日本で普及したのか?

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
軽自動車がこれほどまでに日本で普及した背景には、その歴史と制度が深く関わっています。
戦後の「国民車構想」を背景に誕生した軽自動車は、当初360ccという小さな排気量でした。
1970年代に入ると、より安全で高性能な車を求める声に応え、規格は550ccへと拡大されます。
この時代に、アルト(スズキ)が47万円という驚異的な低価格で登場し、軽自動車ブームの火付け役となりました。
そして1998年、安全基準の強化(特に衝突安全性能の向上)のため、ボディサイズと排気量が再び見直され、現在の「660cc・幅1.48m」という規格が誕生しました。
この規格拡大により、軽自動車は「安かろう悪かろう」というイメージを払拭。
室内空間は劇的に広くなり、走行安定性や安全性も飛躍的に向上しました。
さらに、一貫して続いている「税制優遇」。
これが、経済性を重視する多くの日本人ユーザーのニーズと合致しました。
また、日本の「狭い道路事情」において、小回りが利き、駐車もしやすい軽自動車のコンパクトさは、地方の生活の足として、また都市部のセカンドカーとして、欠かせない存在となったのです。
軽自動車の日本国外展開と他国のミニ車種との違いを解説
「K-Car」や「Kei car」として海外の自動車ファンにも知られる軽自動車ですが、これは基本的に日本独自の規格です。
税制優遇とセットになったこの細かな規格は、他国にはほとんど例がありません。
過去には、スズキのアルトやダイハツのミラなどが、アジア市場を中心に輸出・現地生産された歴史もあります。
しかし、それは必ずしも日本の軽自動車規格のままではなく、現地向けに排気量を800ccや1,000ccに拡大したモデルが主流でした。
ヨーロッパにも「Aセグメント」と呼ばれる小型車(例:フィアット500、スマート フォーツー、トヨタ アイゴXなど)が存在します。
これらはサイズ的には軽自動車に近いものもありますが、排気量は1,000cc前後が主流であり、日本の軽自動車のような厳格な規格や大幅な税制優遇はありません。
あくまで市場のニーズとして「小さな車」が選ばれているという点が、法律と制度で守られている日本の軽自動車との大きな違いです。
軽自動車と類似規格の海外ミニカー・市販Nシリーズの比較
ヨーロッパには、「マイクロカー(ミニカー)」と呼ばれる、さらに小さな車両区分が存在する国もあります(例:フランスのリジェ、エグザムなど)。
これらは、国によっては自動車免許がなくても運転できる場合があるなど、日本の軽自動車とはまた違った位置づけの乗り物です。
一方、日本の軽自動車市場に目を向けると、近年圧倒的な人気を誇っているのが、ホンダの「Nシリーズ」(特にN-BOX)です。
N-BOXは、軽自動車の規格(全長3.4m以下、全幅1.48m以下)という限られた枠の中で、独自の「センタータンクレイアウト」技術などにより、常識を覆すほどの広い室内空間と優れた使い勝手を実現しました。
さらに、先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備するなど、安全性や走行性能も小型車に引けを取りません。
こうした「軽とは思えない」高い品質と価値を提供したことが、Nシリーズが多くのユーザーに選ばれ続ける理由でしょう。
▼関連記事
-

-
大人4人が快適に乗れる軽自動車おすすめ10選
「家族や友人と4人で出かけたいけど、軽自動車って本当に快適なのかな?」 「どの車種を選べば後悔しない ...
続きを見る
軽自動車に関するよくある質問&使用者の悩み解決Q&A集

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
最後に、軽自動車に関してよくある質問とその回答をまとめました。
Q1. 結局、軽自動車の正式名称は何ですか?
A1. 法律(道路運送車両法)上の正式な区分名は「軽自動車」です。
車検証(自動車検査証)に記載されている「軽四輪乗用自動車」や「軽四輪貨物自動車」は、「軽自動車」という区分の中での、さらに詳細な「用途車種名」を指します。
Q2. 軽自動車と「軽乗用車」「軽四輪乗用車」は何が違うのですか?
A2. 「軽自動車」が一番大きな括り(規格全体)を指します。
「軽乗用車」や「軽四輪乗用車」は、その軽自動車の中で「主に人を乗せるため」に使われるタイプ(5ナンバーや7ナンバー)を指す言葉です。
日常生活で使われる軽自動車の多くがこれに該当します。
Q3. 軽自動車で高速道路を走るのは不安ですが、大丈夫ですか?
A3. はい、全く問題ありません。 道路交通法上も普通車と同じように走行できます。
ただし、ひと昔前の軽自動車と比べ、現在の660ccの軽自動車(特にターボ車)は格段にパワーアップしていますが、普通車に比べると加速や登坂能力が劣る場面もあります。
車間距離を十分にとり、無理のない速度で安全運転を心がけましょう。
Q4. 軽自動車の後部座席(リアシート)に子供を乗せても安全ですか?
A4. はい、現在の軽自動車は高い安全基準(衝突安全ボディなど)を満たしており、チャイルドシートやジュニアシートも問題なく装着できます。
▼関連記事
-

-
チャイルドシート2台設置するなら?軽自動車おすすめ車種5選
「子どもが2人になったら、今の軽自動車にチャイルドシート2台は乗るのかな?」 「これから買う軽自動車 ...
続きを見る
まとめ:軽自動車の正式名称から最新事情まで一挙総復習

軽自動車&バイクのある暮らし・イメージ
今回は、「軽自動車の正式名称」という疑問を入り口に、その定義から歴史、普通車との違い、メンテナンスに至るまで、軽自動車の魅力を幅広く解説してきました。
【今回のまとめ】
- 軽自動車の正式名称(区分名)は「軽自動車」である。
- 車検証の「軽四輪乗用自動車」などは、その中の「用途車種名」を指す。
- 軽自動車は、法律で「排気量660cc以下、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下」と厳格に定義されている。
- この規格により、税金(軽自動車税など)や高速料金が安いという大きな経済的メリットがある。
- ナンバープレートは黄色(自家用)が基本だが、用途(貨物車)や特別仕様(白ナンバー)もある。
- 運転に必要な免許は「普通自動車免許」でOK。
- 「安かろう悪かろう」は昔の話。現在は室内空間、安全性、走行性能ともに飛躍的に向上している。
「軽自動車」は、ただ小さいだけでなく、日本の法律と文化の中で独自に進化を遂げてきた、非常に合理的で魅力的な乗り物です。
この機会に、ぜひあなたのカーライフの選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。